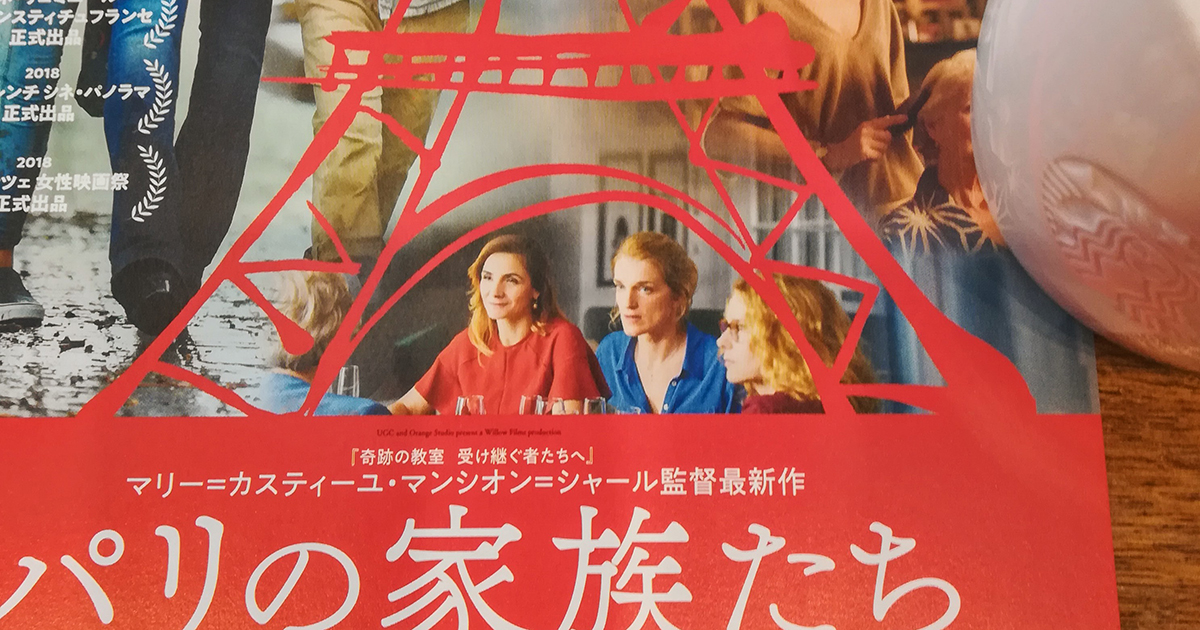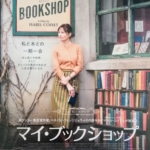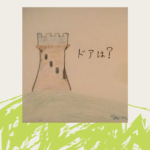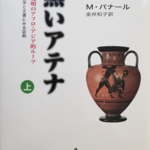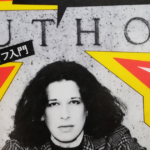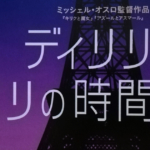お母さん大好きな皆さん こんにちは
矢嶋ストーリーの矢嶋です。
映画『パリの家族たち』を観てきました。
原題は『母の日』 La Fête des mères 。
よかった。👏🏾👏🏾👏🏾
テーマは母。
母が…母に…母の…母は…
母を巡る様々な人生が
輪舞する作品です。
そこには子供や夫の人生も。
母の日に、母について考えよう。
母も人、そして個人。
個人を尊重するフランスらしい映画。
観てほしいので、
⤵︎な感じで、ご紹介します!
では、さっそく!
まずは予告編をどうぞ
こちらです。⤵︎
「すべての女性たちへ」
「きっと家族に会いたくなる!」
邦訳タイトルは『パリの家族たち』。
この作品、プロモーションでは
「女性」「母親」「家族」を超強調。
でも、女性のための映画じゃありません。
この作品のテーマは「母」。
原題は母の日( La Fête des mères )。
母の日という記念日を機会にして、
母という存在に注目。
母って?
そのイメージを広げるために、
母を巡る様々な人生が登場します。
母を通して子供、
娘や息子の人生を描きます。
母になった妻に焦点を当て、
パートナーである夫の人生に
光を当てます。
母を慕う息子の人生が
取り上げられます。
母でない時間を生きる母、
つまり、彼女個人の人生が
クローズアップされます。
母はずっと母でなくては
いけないのでしょうか。
母になったら、
母でない人生を
あきらめなくては
いけないのでしょうか。
こう問いかけながら物語は、
この作品の本当のテーマに
近づいていきます。
その意味で、
邦題『パリの家族たち』も
予告編のキャッチコピーも
的外れなのですが、
その話は最後に書くことにして。
作品の雰囲気をもう少し。
ネタバレしない程度に
紹介することにしましょう。
様々な人生が輪舞します
さきほどチラッとふれたように、
この作品には、
多くの人の人生が登場します。
主人公は一人ではありません。
たくさんの人が主人公です。
女性も、男性も、主人公です。
母も、息子も、主人公です。
二人が実の親子でも、
二人の人生は別々で。
母親の人生を描くときは
母親が主役。そして、
息子の人生を描くときは
息子が主役。
そういう人生の描き方を
この作品はするのです。
そんな人々の
いろんな人生。
女の、男の、子どもの、老いた人の…
様々な人生が
チョコチョコ、チョコチョコ。
いくつも登場します。
ひとつの人生が描かれ
「そうなんだぁ」と思う頃、
話は別の人生に替わり
「そうなんだぁ」とまた思い、
わかりかけてきたところで、
また別の人生が描かれます。
ひょっとしてオムニバス映画?
(オムニバス:別々の作品を束ねる)
と思いきや、全然違っていて。
前の人生が再び登場します。
その人生は、
今スクリーンに映し出されている
別の人生と、
くっついていたりします。
そのイメージは…
それぞれの人生が踊り手(:💃🏽🕺🏻)だとすると、
彼らが「この作品」という大広間に集まって、
💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻
💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻💃🏽🕺🏻
ロンドな曲(例 モーツアルトのアイネ・クライネ・
ナハトムジークの第4楽章 →YouTube)で
輪舞しているような。
輪舞の途中で、「母」を合図に
お互いが手を繋いだり、離したり。
そんなクロスオーバーが
静かに続くような。
母の、母が、母で、
母に、母は、母へ、
母と、母を、…
を眺めているような
映画なのです。
母とは? なに?
その、たくさんの人生の中に、
母であることを忘れたい人生
が登場します。
このライフスタイル。
良妻賢母を美徳とする日本では、
嫌悪されがちですが、
この映画では
「それのどこが悪いの?」
と堂々と問いかけます。
「人生の中に、
母である部分があるし、
それはそれで楽しいし、
充実しているけど、
そうでない部分もある!」
と主張します。
「もちろん、子供にとって母親が
どれほど大切かは分かっている。
でもね…」
「いつまでも、わたしに
母を期待しないで」
「母は、本日で、もうお終い」
と、心のうちを披露するのです。
えぇっ?と思うかもしれませんが、
観ているうちに、すごく納得します。
そして、ラストシーンに
😂😂😂🤣してください!
この作品の原題は、母の日です。
「個」を尊重する人生に乾杯 🥂
それにしても。
フランスらしい映画だと思います。
個を尊重して。個が強くて。
わたしは、わたし。
自分があって、母である。
その逆はあり得ない。
期待されても困る。
人はそれぞれ。
人生もそれぞれ。
このクールさ 🥂 に
愛情が流れ込んでくる、🥂🥂
そんな雰囲気の作品でした。
ご紹介が遅れました。
監督は、
マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール
Marie-Castille Mention-Schaar さん。
『奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』Les Heritiers も
彼女の作品です。⤵︎
マリーさんは、人物より人生、
人生より社会、を描く人で、
「こういうの、いいんじゃない!」を
作品のテーマにする人です。
今回の『パリの…』では、
「母」を通して「個人」を描き、
「社会」を見つめ直しました。
なのに、どうして、日本の配給会社は
原題の「母の日」を避け、
『パリの家族たち』をタイトルに
したのでしょう?
パリ🇫🇷の特別感? フライヤー⤵︎を
見るとそんな感じもします。
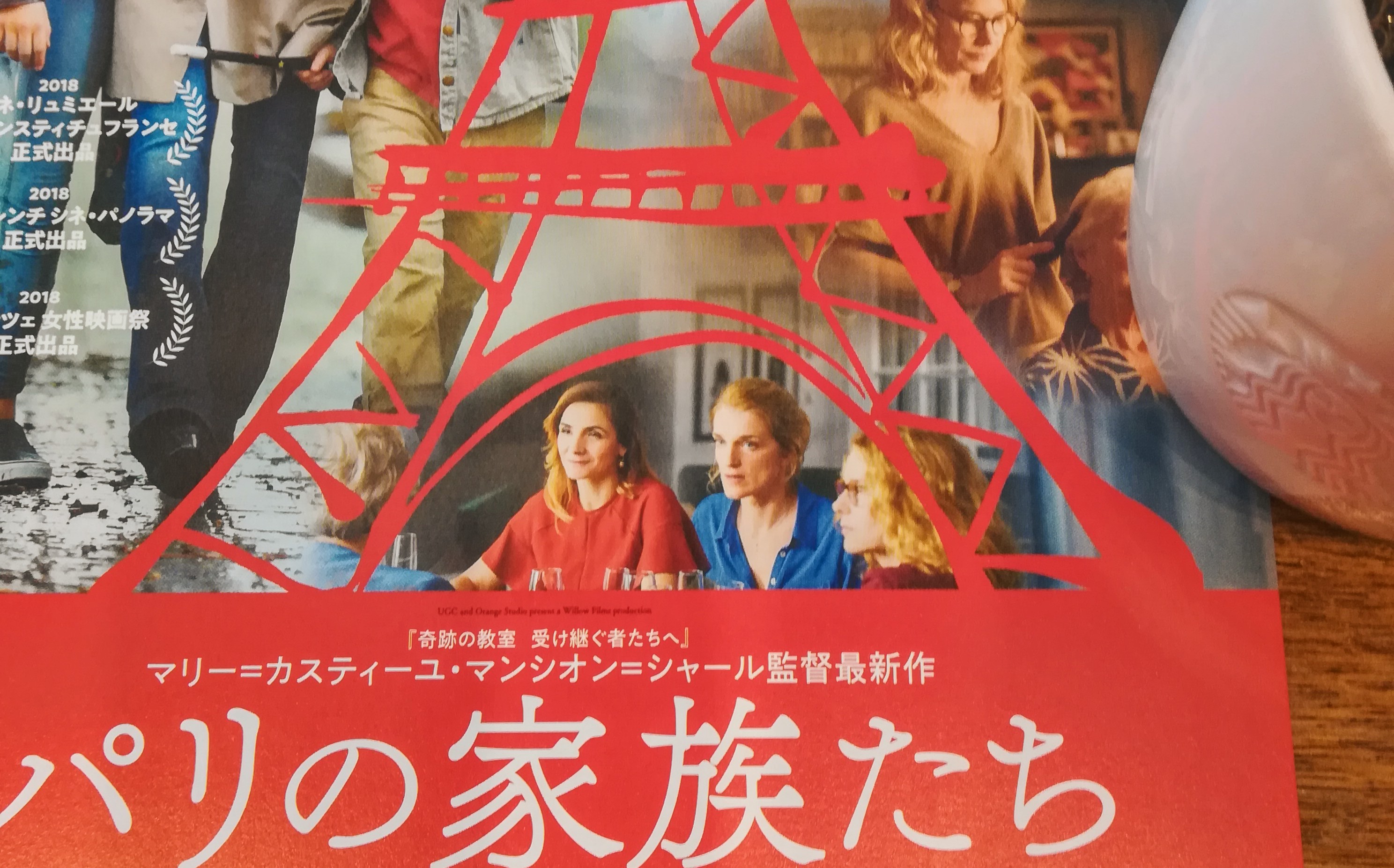
でもパリだから!って話でもないし、
家族の話じゃなくて、
個々の人生の話だし。
タイトルは原題通り『母の日』。
そうでなければ
La Fête des mères のカタカナ読み
『フェットゥ デ メー』のほうが
内容、伝わる!
と、わたしは思うのですが、
みなさんはどう思われますか?
と、いろいろ書き散らしましたが、
いい作品であるのは間違いなし。
ぜひご覧ください。
矢嶋ストーリー
矢嶋剛
P.S. 余談です。
この作品に「通りの奥のほうから、
妊娠した若い女性が歩いてくる」
シーンがあるんですが、彼女、
『奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』で
教室の一番前に座っていた人に
とても似ていたんです。
(ご本人かなぁ?)