世界中の読者のみなさま、こんにちは
矢嶋ストーリーの矢嶋です。
今日は、あらためて
ご挨拶と御礼をしたいのです。
ついに完結しました。
お客様😊の最上ヒントを
500円(=1コイン)で
ご提供してきた
マーケティング・1コイン・シリーズ
marketing 1coin series 。🪙📚🔗
第1巻(vol.1)
『マーケティングは正直バナナ』
から始まり、
第14巻(vol.14)
『ボスと会社とお客と習慣』
の刊行を持って、
全15巻を完結させることができました。⤵︎
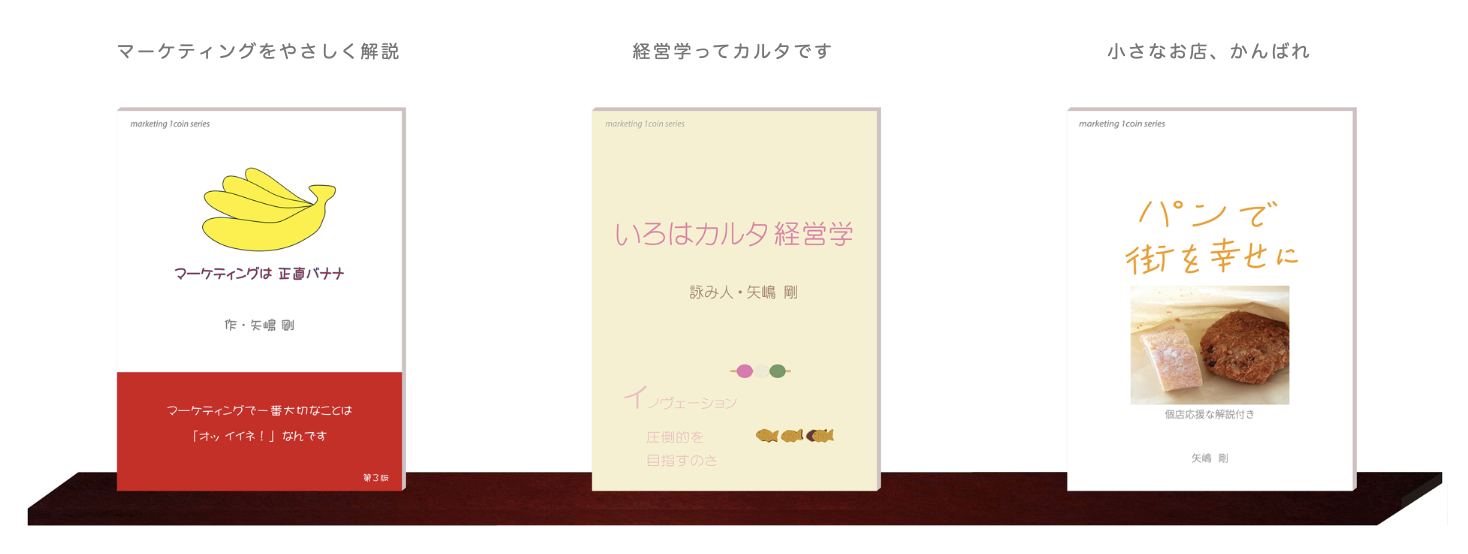
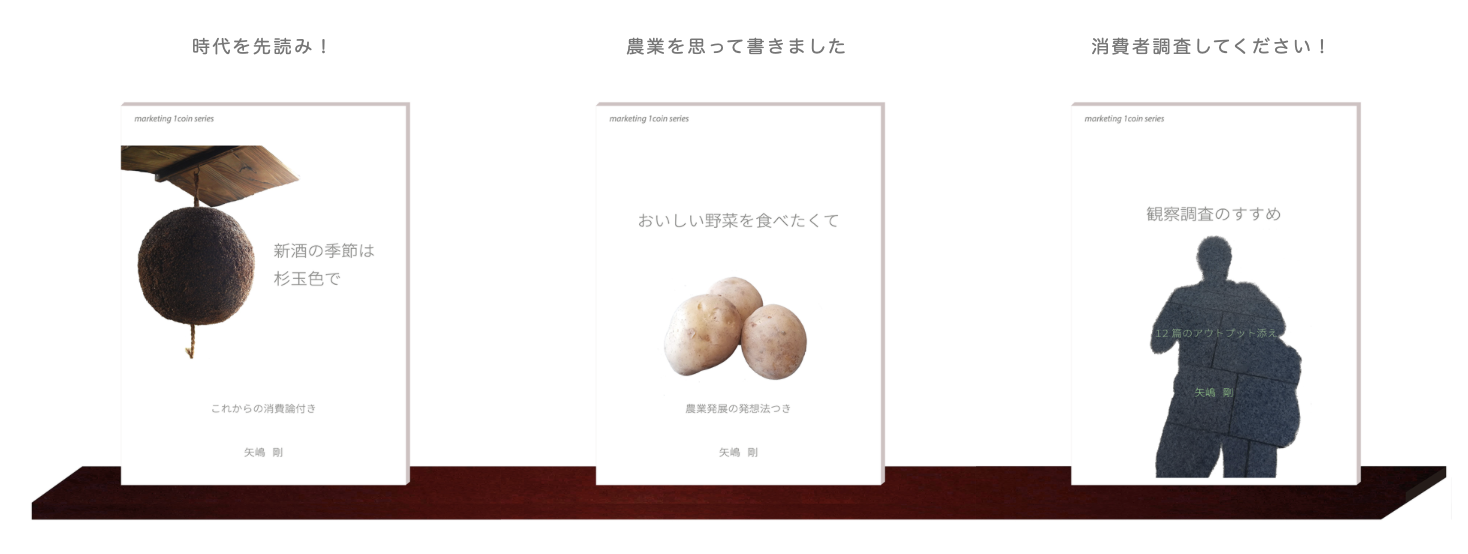
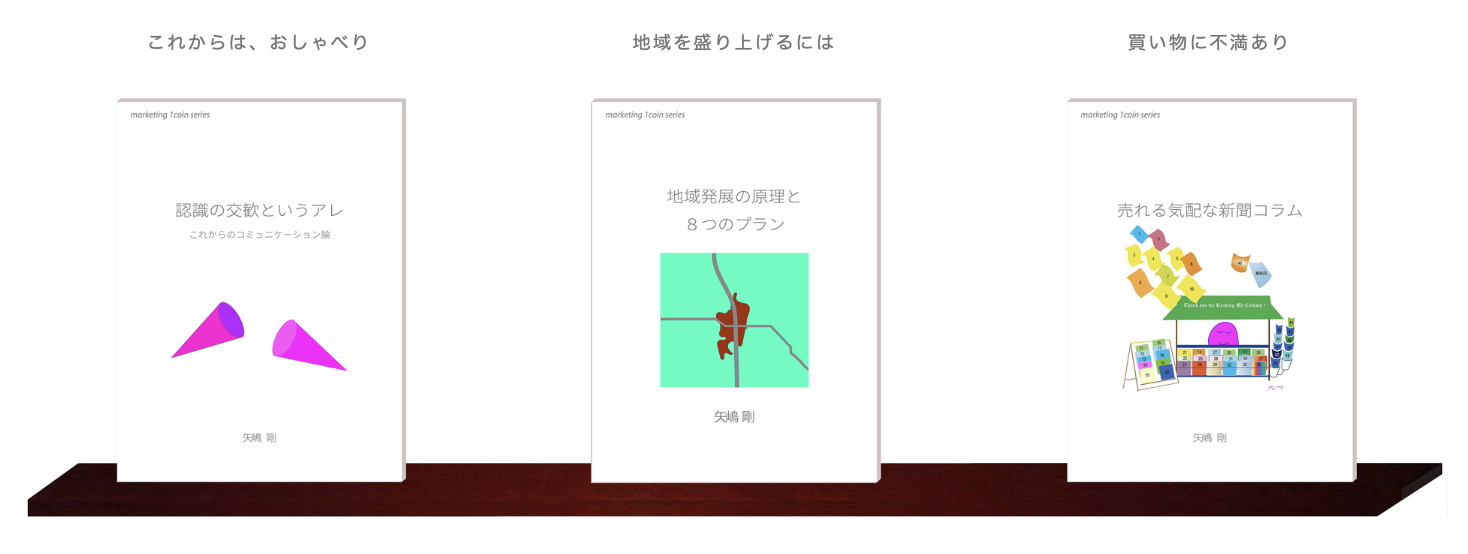
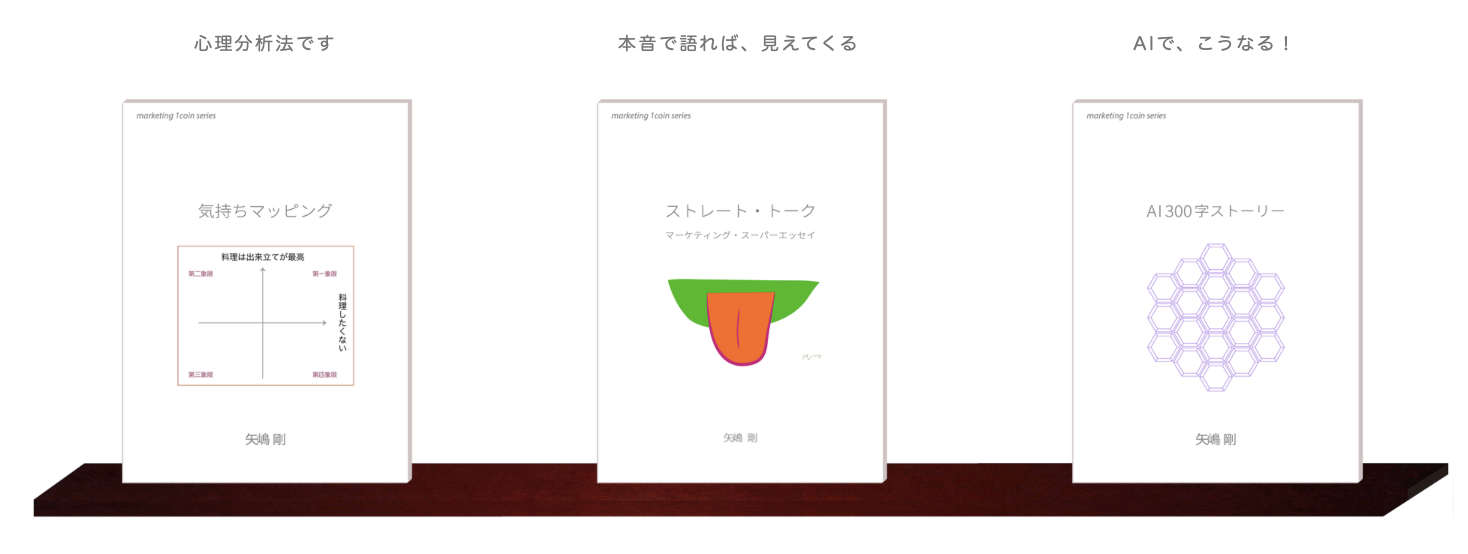
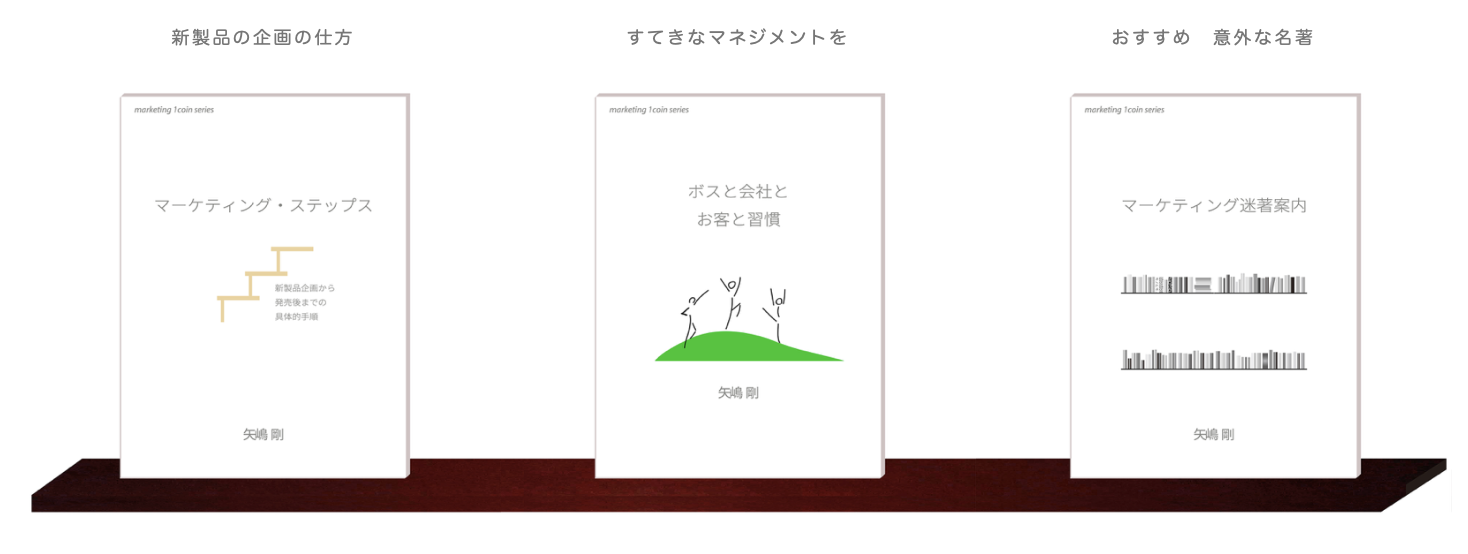
心より御礼を申し上げます。
ありがとうございました!
みなさんあっての完結でした。
「ちょっと待ってよ」😤
「なに、一人で浮かれんてんのよ」🤨
「完結って、何?」🤯
「完結したら、その後、どうするの?」😬
「ちょっと、教えなさいよ」😡
ごもっともです。
勝手に「終わり!」と言われても…
承知しました。お答えします。
以下の流れで、お話しします。
よろしくお願いいたします。
最初に、完結についてお話しします。
完結って何?🤯
実は、シリーズ化を決めたときから
完結のこと、考えていました。
「何事にも終わりはある。
じゃあ、どうする?」
みたいに。
矢嶋ストーリーの目指してきた地平、
学校とか行かなくても、
どんなに忙しくても、
お金なくても
知りたいことを学べるように!
実践できて、効果があって、
これからの仕事に役立つことを!
そう思って、先にテーマを選んで。
それが、この15冊の起点になりました。
お堅い言葉で書けば、
(絶対にそんな風には紹介しないけど)
(わかりやすい記述はアホ!と思う、
歪んだプライド持つ人に向かって書くと)
マーケティングの核心、経営学の課題と本質、
競争戦略の策定、ライフスタイル予想法、
危機管理と対策立案、社会調査の活用法、
コミュニケーションの本質と戦略、
地域振興プランニング、
不満分析=ニーズ発見法、
複雑な心理の分析方法、
原点回帰とリストラクション、
最新技術への対応法、
マーケティング・マネジメント(矢嶋版)、
マネジメント(組織運営)改良法、
本を介したリベラルアーツへの接近、
を網羅したことになります。
(15巻の詳細は →🔗)
おかげさまで、どの本も、
矢嶋っぽく、矢嶋ストーリーらしく、
(超わかりやすく、核心ズバリの)
😆😂🤣(だははは)モードで、
書き上げることが出来ました。
知りたい方へ、大切なすべてを
お届けする準備が出来ました。
あとは
気づいていただき、
応用していただくだけ。
まぁまぁ、これで、
たいがいのこと、
行けるんじゃないかな。
問題に
対処できるんじゃないかな。
15冊を、全部読み返して、
あたらめてそう思ったので、
これで予定通り「おしまい」にしよう。
なので、
「完結」という言葉を
使わせていただきました。
本は終わり
今から書くことは打ち明け話みたいで
ちょっと恥ずかしいのですが、
完結して。書き終えて。
ちょっと達成感、あります。
やれるところまで、
やった!みたいな。
学問の神様がいらして、
「今まで経験したこと、
学んできたことを
書き遺したか?」
と尋ねられたら、
「全部、出し切りました」
そう、お答えできる。
それくらいの15冊になりました。
どれも短い作品ばかりですが、
短いからこそ、練り直しや書き直しも
けっこう多くて。
みなさんが試せる、実利になるヒントを
腑に落ちるように書くっていうもの、
実際書いてみると、大変でした。
とはいえ、書けちゃったので、
祝杯、あげちゃいました。
乾杯! 🥃
こういうときは断然、スコッチ。
おつまみは不要。
それにしても、よく書いたなぁ。
(ちょっと、しみじみ)
最終巻
『ボスと会社とお客と習慣』の一節
「ゴミを拾う」なんか、
詩のように書いちゃいました。
それがいちばん伝わると
思ったから。
でも、その詩めいた短文が
マネジメント(組織運営)の
処方箋なんです。
自分で書いたくせに
ちょっと驚きです。
そして、けっこう疲れ切っていて。
まことに勝手ではありますが、
お客様😊関連で書く
本というスタイルは、
『ボスと会社とお客と習慣』をもって
最後にしようと思っています。
おそらく、この本が、
マーケティング関連で書く
矢嶋の終作になると思います。
今後、どうする?
もちろん、
知りたい方、学びたい方への応援を
やめるつもりはありません。
矢嶋ストーリーを
クローズするつもりもありません。
本を読んでくださった方からの
ご感想やご質問に
今まで通り、お答えいたします。
(詳しくは →🔗)
時間が取れず、手が回らなかった
「マーケティングの知見メモ」→🔗
に新しいメモを加えていこうと
思っています。
本以外のスタイルで、
お客様😊のヒントを
発信できるんじゃないかな?
なんて考えてもいて。
長い話は、
このたい焼きblogに投稿。
短い話はBlueskyに
300字弱で投稿。→🔗
そういう方向で
動こうと思っています。
応援、続けます
ちょっとスコッチが効いてきたかな?
ヘトヘトなときに🥃だと
こうなる気がします。
🌲🌲🌲🐑🐏
えぇっと…
「売らんかな」の技巧が学問のフリをし、
ズルをすることを推奨する学者の本が出る、
まことに情けない今の世の中ですが、
お客様😊(=働く人😊)のために
書いてきた、このシリーズが
一条の清涼になれば!
真面目に働く方のハートに
灯🕯️を付ける機会になれれば!
そう願いながら、
マーケティング・1コイン・シリーズは
その執筆の幕を静かに下ろしたいと
思います。
それでは失礼いたします。
深々と礼。
矢嶋ストーリー
矢嶋 剛
